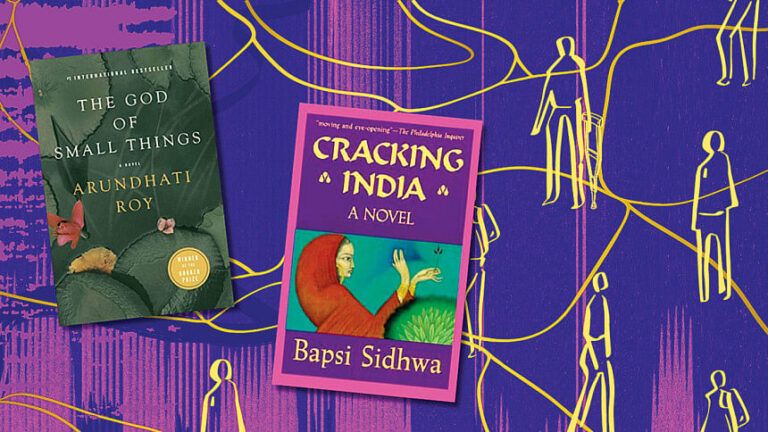[The Daily Star]障害者を他者化し、「標準」のグループから「例外」のグループに押し出すという生来のプロセスについては、言及すべきことがある。身体が政治化され、理想的な身体より「劣る」または「異なる」と見なされるものはすべて追放者とみなされる可能性があるというのは、私たちが毎日目にする文化的、政治的な慣習である。障害のある身体は人間以下の存在として扱われることが多く、疎外され社会的に追放された存在を文学で描写すると、そのような社会的、文化的規範を証明できることがある。
バプシ・シドワの『インドを破る』(1988年、初版は『アイスキャンディーマン』)は、1947年のインド分割の混乱期を舞台にしており、主人公のレニーは幼少時にポリオに罹患し、その結果、特定の障害を負ったパーシーの子供です。小説の冒頭では、レニーの障害が物語の中心となっています。レニーの両親が望んだほどの運動能力は一連の治療によって得られなかったため、担当医のバルーチャ大佐はレニーに「幸せで気楽な人生」を送るよう勧めます。
彼女の願望、動機、目標が身体障害と結びつき、その重荷になるという考えは、障害に対する認識の障害者差別的な性質を描写しており、したがって、健常者は障害者より優れているという考えであり、バルーチャがレニーに対して、彼女のために重要な人生の決定を下す力を与えている。
教育や職業のない幸せな夫婦生活は、ある人にとっては完全に充実した人生かもしれないが、レニーには人生の進路を決める主体性がほとんど、あるいはまったくなく、彼女に代わって決定を下した人たちは、障害を負うことに慣れておらず、結婚して教育を受けないことが充実した人生のための最善の道だとも考えていなかったことを考慮に入れなければならない。もちろん、レニーのポリオは彼女が教育を受けるのを妨げるものではない。むしろ、教育を受けること、あるいはそれ以上の努力をすることは「神経を緊張させる」ので、彼女は結婚して子供を産むことを望み、それで幸せになるべきだという思い込みである。
彼女の願望、動機、目標が身体障害と結びつき、その重荷になるという考えは、障害に対する認識の障害者差別的な性質を描写しており、したがって、健常者は障害者よりも優れているというものであり、バルーチャがレニーに対して重要な人生の決定を下す力を与えている。
小説の中でレニーがバルーチャと会う2回の合間に、シドワは「幸せなひととき」について触れている。ここでは、4歳のレニーはいとこと一緒に学校に通っており、先生をだまして障害があるのはいとこだと信じ込ませ、他の子供たちと遊ばせる。レニーが叫んだり、遊んだり、笑ったり、つま先で走ったりする様子から、彼女が一般に思われているほど運動能力や機能を失っていないことが分かる。レニーは、障害の不均衡な重荷、もっと正確に言えば、両親から押し付けられた障害への恐怖の重荷を振り払えるとき、幸せである。
サイエドアフリン・タランナム は、キャンパス、新星、スターユース の副編集者です。
彼女の願望、動機、目標が身体障害と結びつき、その重荷になるという考えは、障害に対する認識の障害者差別的な性質を描写しており、したがって、健常者は障害者より優れているという考えであり、バルーチャがレニーに対して、彼女のために重要な人生の決定を下す力を与えている。
バールーチャ大佐がすぐに「まったく普通」だと安心させたことで、障害のある人を普通ではないとみなすという現象が確立され、紹介されました。つまり、「完全」で「理想的」と見なされるものと少しでも異なる身体を持つ人は異常であり、「直す」必要があります。さらに、バールーチャ大佐はレニーを「負担のない」生活に制限することに決めました。彼女の両親を彼女の病気が永続的であるとして慰めながら、彼は彼女が教育を受ける必要はなく、いつでも結婚して幸せな生活を送ることができると言います。これらすべてにおいて、彼女の障害はレニーが落ち着く必要がある原因にされ、障害のある生活はより良いものやより高い成果を必要とせずに平凡なものに減らさなければならないとほのめかしています。
教育や職業のない幸せな夫婦生活は、ある人にとっては完全に充実した人生かもしれないが、レニーには人生の進路を決める主体性がほとんど、あるいはまったくなく、彼女に代わって決定を下した人たちは、障害を負うことに慣れておらず、結婚して教育を受けないことが充実した人生のための最善の道だとも考えていなかったことを考慮に入れなければならない。もちろん、レニーのポリオは彼女が教育を受けるのを妨げるものではない。むしろ、教育を受けること、あるいはそれ以上の努力をすることは「神経を緊張させる」ので、彼女は結婚して子供を産むことを望み、それで幸せになるべきだという思い込みである。
彼女の願望、動機、目標が身体障害と結びつき、その重荷になるという考えは、障害に対する認識の障害者差別的な性質を描写しており、したがって、健常者は障害者よりも優れているというものであり、バルーチャがレニーに対して重要な人生の決定を下す力を与えている。
小説の中でレニーがバルーチャと会う2回の合間に、シドワは「幸せなひととき」について触れている。ここでは、4歳のレニーはいとこと一緒に学校に通っており、先生をだまして障害があるのはいとこだと信じ込ませ、他の子供たちと遊ばせる。レニーが叫んだり、遊んだり、笑ったり、つま先で走ったりする様子から、彼女が一般に思われているほど運動能力や機能を失っていないことが分かる。レニーは、障害の不均衡な重荷、もっと正確に言えば、両親から押し付けられた障害への恐怖の重荷を振り払えるとき、幸せである。
さらに、先生が子どもたちに「病気」なのは誰かと尋ねるとき、たいていは障害のない多くの人々と同じように、先生も無意識にその言葉を口にしている可能性が高い。レニーは病気ではなく、症状を引き起こしたり、すぐに治療や医療処置を必要とするような病気にかかっているわけではない。
たとえ短い言葉であっても、この「病気」という言葉の使用は、さまざまな病気や疾患を抱えた人々と障害者を同じ傘の下にまとめようとする社会の類似性と意欲を描写するだけでなく、政治団体の階層的二分法(健常者/障害者団体)を正当化し、その結果として例外に対する規範、または理想的でない者に対する理想の覇権を正当化する傾向がある。
こうした偏見と、こうした社会構造に伴う根深い優越感こそが、権力の不均衡を生むのです。結局のところ、植民地主義の遺産と植民地との接触を考えると、どんな集団でも権力の不均衡が生じようとする傾向が常に存在します。人は、自分の特権を、その特権を持たない人々に対する権力の源泉に変えたいと常に思うものです。
たとえば、アルンダティ・ロイの『小さな神』(1997年)に登場するヴェルーサというキャラクターは、共産主義者で「不可触民」(主人公アムとその家族よりも低いカースト)である。家族の工場で働くために雇われた大工であるヴェルーサの人生は、彼の社会的・政治的立場に完全に絡み合っており、最終的には上位カーストのアムとの関係によってひっくり返される。アムの双子の1人で、ソフィー・モルの葬儀のときにヴェルーサを愛したラヘルでさえ、誰かが教会の高いドームに絵を描いているところを想像し、「ヴェルーサのような人」がそれをやったに違いないと自分自身で考え、彼を社会の下位カーストの人たちと分類する。
本書の第 11 章にあるアムの夢の中で、ヴェルーサは片腕しか持っていない。アムの夢の中では、彼の行動は「障害」によって制限されており、その結果は影響がないと説明されている。「彼は砂に足跡を残さず、水に波紋を残さず、鏡に姿を映さなかった。」明らかに疎外された障害を持つ人物であるヴェルーサを恋人の夢の中で描くという選択には意味がある。
彼の夢の中の障害を最も文字通りに解釈すると、その障害は、自分の望みや意志を実行するための手段も手段もないことを暗示するものとなる。片手がないことは、彼が常に選択を迫られていることを示している。彼はすべてを手に入れることはできないが、そうできるはずだ。それは彼が迫られている選択の性質も示しており、彼には交渉力がほとんどないかまったくなく、状況を改善することは彼の手に負えない。
彼が夢の中で障害を負っていることは、ポスト植民地時代の人種・民族差別の状況と、障害のある身体に課せられた不可能な困難とも比較できる。夢を通して、彼が常に監視されているという考えを解釈することができ、その光景はパノプティコンを彷彿とさせる。
また、この障害はヴェルーサにのみ現れ、アムには現れていないことにも注目すべきです。これは、彼らが置かれている状況を直接的かつ意図的に言及しており、明確な対比を描いています。ヴェルーサのカーストと政治思想のせいで、彼らは両方とも精査の対象となっていますが、ヴェルーサの方が不利な立場にあり、行動力にも大きな制限があります。
最後に、アムはヴェルーサの足跡や波紋のなさについて言及していますが、その点について、ヴェルーサと夢の中の障害を持つ彼にとって、それは彼に痕跡が残されていないことを表していると私は主張したいと思います。社会とアイエメネムにおける不可触民としての彼の存在は、共産主義への抗議とその後の彼の死に関して、その糸に、そしてインドのより大きな組織に、ほとんど、あるいは全く痕跡を残しません。
したがって、ロイとシドワの作品を通して、私の主張は成り立つ。障害の描写は、書かれている以上のものであり、選択とアイデンティティに基づいて社会から切り離され、押しのけられた人々の生活を反映することを可能にする効果的なツールである。
過去数ヶ月、バングラデシュでは、当初は自由を求める戦いだったものが、後に必死の改革要求へと変わり、かなりの混乱が巻き起こっています。特にここ数日のリンチ、暴徒裁判、コミュニティ間の暴力の報告を見ると、正義の名の下に報復しようとするのを私たちが集団で止め、社会が価値がない、または「劣っている」とみなした人々に対する支配と権力を獲得したいという私たちの本来の欲求によって、さらなる分裂を生むのを止めることはできるのだろうかと疑問に思います。
サイエドアフリン・タランナム は、キャンパス、新星、スターユース の副編集者です。
Bangladesh News/The Daily Star 20240926
https://www.thedailystar.net/daily-star-books/news/falling-through-the-cracks-the-normal-3712411
関連