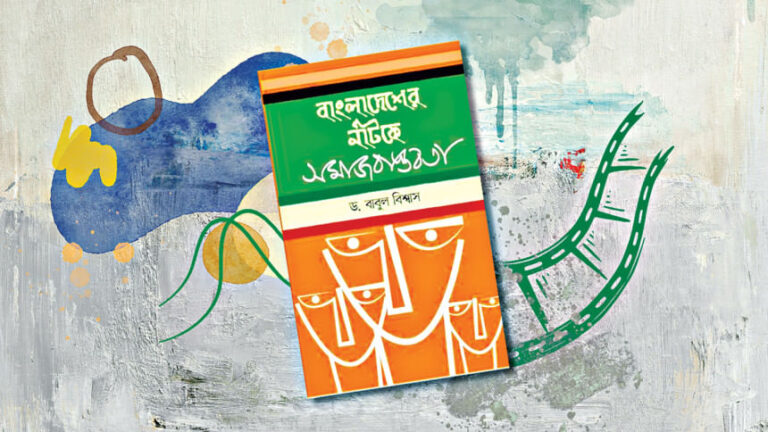[The Daily Star]バングラデシュの演劇は、単なる娯楽の一形態ではありませんでした。常に社会を映し出す鏡として、その矛盾、闘争、そして願望を映し出してきました。バブール・ビスワス博士は、博士論文を翻案した代表作『バングラデシュ人のナトケ・ショマイバストボタ』において、バングラデシュの演劇が歴史を通して、特に独立後の社会の現実とどのように関わってきたかを探求するという野心的な課題に取り組んでいます。その成果は、学術的かつ分析的であり、現代の文化的言説にも深く関連する啓発的な研究となっています。
冒頭でビスワス博士は、自身の作品を流動的な国家という文脈の中に位置づけています。博士は、バングラデシュの独立は、共同体間の緊張、覇権主義的支配、そして帝国主義的策略という試練の場の中で生まれたことを私たちに想起させます。こうした構造的な力に加え、新たな形態の消費主義と宗教的独断主義が社会意識を再構築しました。こうした背景の中で、演劇は文化的実践としてだけでなく、抵抗の形態、そして社会への批評の手段としても出現したのです。
この本では、著名な劇作家のセリム・アル・ディーンが、演劇を社会学的、歴史的観点から枠組みを作ったとされており、ビスワス博士もこの系譜に沿って自身の分析を展開している。
本書の射程範囲は実に広範である。ビスワス博士は、バングラデシュ演劇を植民地主義、消費主義、覇権主義といった世界的なプロセスと対比させることで、この国の文化的闘争が孤立したものでも特異なものでもないことを示す。
本書は5つの重要な章から構成されており、それぞれがバングラデシュ演劇における異なる時代的研究を扱っています。冒頭の章では、パーラ朝時代から中世、植民地時代、そしてポストコロニアル時代に至るまでの文化的慣習を辿りながら、歴史的に概観します。この長い歴史の軌跡は、政治的・宗教的権威の変遷が文学と演劇研究にいかに永続的な影響を及ぼしてきたかを明らかにしています。特に印象的なのは、イギリス植民地支配下で西洋の演劇的伝統がどのように取り入れられ、ベンガル演劇の方向性を徐々に変化させていったかという分析です。ビスワス博士は、これらの変遷を階級、支配、アイデンティティといった問題と注意深く結び付け、後の議論の確固たる基盤を築いています。
第2章では、イギリス統治以前からパキスタン独立までの時代における、独立以前の演劇を考察します。ここでは、演劇が植民地主義と権威主義体制に対する文化的主張の場として提示されます。1952年の言語運動とその後の文化的闘争は、単なる政治的出来事としてではなく、演劇の革新の触媒として提示され、演劇がいかにアイデンティティと自律性を求める闘いを前進させたかを示しています。
しかし、本書が真に活気づくのは第3章と第4章である。独立戦争とその後の激動の時代に焦点を当て、ビスワス博士は演劇がいかに国家の危機を吸収し、表現してきたかを探求する。「エクティ・ミヒル」のような戯曲は、バングラデシュの誕生、戦争のトラウマ、そして新たな社会のビジョンを凝縮した重要なテキストとして強調されている。独立戦争をテーマにした戯曲は詳細に検討され、それらがナショナリストの願望だけでなく、その後の幻滅をどのように反映していたかにも注目している。ビスワス博士は、独立後の演劇は、宗教の操作、権威主義的支配の台頭、そして消費主義の蔓延が批判的に検証される場となったと主張する。劇作家たちが採用したリアリズムの枠組みは、裏切り、不安定さ、そして価値観の変容に苦しむ社会の生きた経験と深く結びついていることを示す。
本書の最も魅力的な点は、おそらく第5章で、演劇における女性を前面に押し出している点にある。ビスワス博士は、独立後のバングラデシュにおいて、女性の平等とエンパワーメントの約束はほとんど果たされなかったと主張する。それどころか、宗教的保守主義と資本主義的消費主義という二重の圧力の下、女性たちは新たな形の抑圧にさらされた。博士は3つの戯曲の分析を通して、自由、承認、そして尊厳を求める女性たちの闘いが舞台上でどのように表現されたかを示す。さらに重要なのは、博士が独立後の演劇を再構築し、女性が単なる登場人物ではなく、文化的物語の創造者となるよう促した女性劇作家の役割にも光を当てている点である。
ビスワス博士は方法論的に厳格なアプローチを採用しています。テキスト分析、アーカイブ資料、関連書籍、専門家へのインタビューに依拠することで、文学批評と社会科学の視点を融合させています。新たな理論的枠組みの適用は研究に新鮮さをもたらし、歴史的連続性と現代的変化の両方に細心の注意を払うことで、バランスの取れた視点を確保しています。
本書の考察範囲は実に広範である。ビスワス博士は、バングラデシュ演劇を植民地主義、消費主義、覇権主義といった世界的なプロセスと対比させることで、この国の文化的闘争が孤立したものでも特異なものでもないことを示す。むしろ、それらは大陸をまたぐ抵抗と適応という、より大きな物語の一部なのである。しかしながら、博士は地域性を見失うことなく、ベンガル人のナショナリズム、文化慣習、そして歴史的経験という特殊性に分析の根拠を置いている。
本書が特にタイムリーなのは、今日のバングラデシュとの関連性にある。宗教的過激主義、ジェンダー不平等、そして消費主義的価値観との闘いを続けるバングラデシュにおいて、演劇は依然として考察と批評のための重要な場となっている。ビスワス博士は、私たちの演劇が歴史的にこれらの課題にどのように対応してきたかを示すことで、より公正で意識の高い社会の形成において、演劇が今後も役割を果たし続けることを暗に訴えている。
本書は、バングラデシュの演劇研究と文化史の分野に計り知れないほど貴重な貢献を果たすものである。文学や演劇研究の研究者や学生だけでなく、文化、政治、社会の交差点に関心を持つあらゆる人々にも訴えかけるだろう。ビスワス博士は、学術的厳密さと文化的意義を併せ持つ著作を著した。本書は、バングラデシュ演劇が芸術としてだけでなく、社会の現実を鮮やかに記録した重要な記録として認識されることを確かなものにしている。
アブドゥス・セリムは著名な学者であり翻訳家です。連絡先は selim70plus@gmail.com です。
Bangladesh News/The Daily Star 20250925
https://www.thedailystar.net/books-literature/news/bangladeshi-theatre-sociopolitical-study-3993946
関連