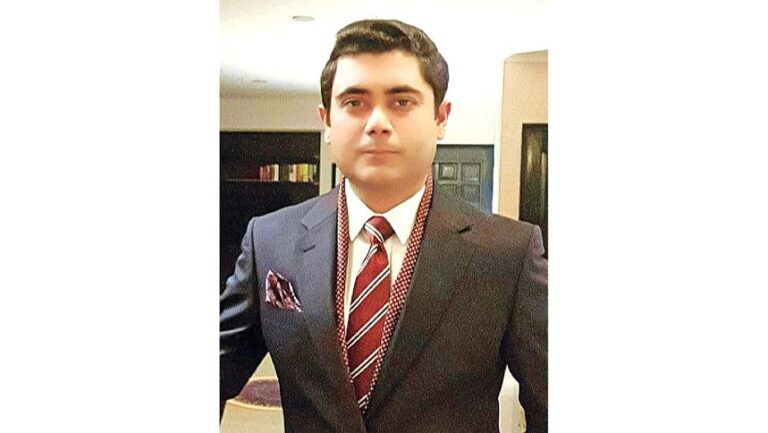[The Daily Star]なぜある国は繁栄する一方で、他の国は貧困や停滞に陥っているのでしょうか?アルゼンチンや南アフリカのように、かつては有望視されていた国々が、なぜ勢いを維持するのに苦労しているのでしょうか?そして、日本や中国のような国々が永続的な経済変革を達成できるのはなぜでしょうか?
これらは政治経済学における最も根深い謎の一つであり、今日に至るまで明確な答えは得られていません。さらに、今後数十年で変革を目指すバングラデシュのような国にとって、これらの問いは本質的に不可欠であるだけでなく、手段的にも根底を成すものです。
数十年にわたる研究にもかかわらず、ある国々が発展の階段を上る一方で、他の国々が下がったり停滞したりしている理由を完全に説明する説得力のある単一の理論は存在しない。
それは地理的な要因によるものでしょうか?歴史的な不正義によるものでしょうか?不適切な政策選択によるものでしょうか?それとも、トランプ政権の関税政策を目の当たりにすればそう主張できるかもしれないが、富裕層によって、そして富裕層のために設計された世界ルールによって、ゲームは不公平に操作されているのだろうか?
内陸国境、厳しい気候、限られた天然資源といった地理的条件が構造的な制約となっていると主張する者もいる。一方で、インドにおける植民地支配やキューバへの数十年にわたる制裁措置を経済衰退や停滞の主な原因として挙げ、外部からの支配を指摘する者もいる。
そして、内的側面もある。国内のエリート層が、イノベーションや生産性を促進するのではなく、レントを搾取するために制度をどのように形成しているかである。豊富な資源を持ちながらも、腐敗政治的な指導者を抱えるコンゴ民主共和国(旧ザイール)は、この現象の教科書的な例と言えるだろう。
重要なのは、これらの説明は互いに排他的ではないということです。歴史の様々な時点で、これらの力が様々な組み合わせで作用してきました。徳川幕府(1603~1868年)時代の日本を考えてみてください。当時は鎖国政策によって貿易や技術革新への露出が制限されていました。あるいは、イギリスの植民地支配下で経済が衰退したインドもそうです。インドは1757年には世界のGDPの約25%を占めていましたが、1947年には5%未満にまで落ち込んでいました。
しかし、他の国々は方向転換に成功しています。1868年の日本の明治維新は劇的な転換を象徴するものでした。政府は絹や造船といった輸出志向の産業を支援するという優先課題を見直し、世界経済への統合を図りました。同様に、中国では1978年以降、強い政治的支持に支えられた経済改革によって、数十年にわたる持続的な産業成長と貧困削減が実現しました。
ここでの教訓は、発展に普遍的な処方箋があるということではなく、成功は往々にして国の適応能力にかかっているということです。高業績国は、後退を完全に避けるわけではありません。むしろ、景気後退を最小限に抑え、世界的な機会を活かすための制度的レジリエンス(回復力)を備えています。彼らは、変化する世界需要に合わせて国内経済を積極的に再構築し、グローバルバリューチェーンに自らを組み込んでいます。バングラデシュのように変革を求める発展途上国にとって、喫緊の課題は二つあります。
まず、自国の進歩を阻害している具体的な障壁(構造的、制度的、政治的など)を厳密に分析する必要がある。次に、慎重かつ大胆な実験を行い、競争力、イノベーション、そしてグローバル統合を促進する政策を策定し、制度を構築する必要がある。
何よりもまず、政策立案者は、発展を阻害する力が動的であり、状況に応じて変化することを認識しなければならない。普遍的なロードマップは存在しない。韓国やシンガポールで成功した方法が、他の国では通用しないかもしれない。自国の発展における制約を深く歴史的に理解し、適応と学習への意欲を持つことが不可欠である。したがって、真に変革をもたらす発展を実現するためには、各国は構造決定論の宿命論と、単純化された政策模倣の魅力の両方を捨て去らなければならない。そうして初めて、各国は自国に根ざしつつも世界的に意義のある道筋を描くことができるのだ。
著者はバングラデシュ政策研究所の主任エコノミストです。連絡先はashrahman83@gmail.comです。
Bangladesh News/The Daily Star 20250416
https://www.thedailystar.net/business/news/why-some-nations-rise-while-others-stagnate-3872096
関連