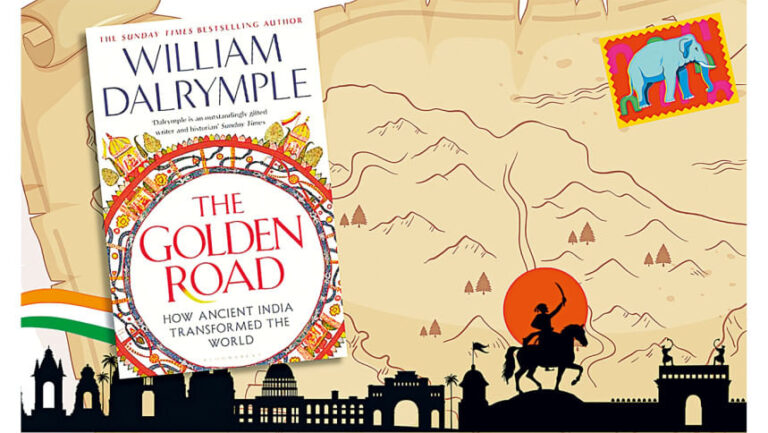[The Daily Star]1025年、南インドのコロマンデル海岸から征服の旅に出た軍艦隊。チョーラ朝ラジェンドラ1世の海軍であり、その目標はベンガル湾の危険な海域全域に広がる、莫大な富を誇ったスマトラ島のシュリーヴィジャヤ王国だった。その後の遠征は驚異的な成功を収め、インド軍は現在のインドネシアとマレーシアにまたがる都市を略奪した。これは驚くべき侵略行為であり、平和で永遠に非暴力を貫いたヒンドゥー教の過去という現代の敬虔な物語とは相容れないものであった。しかし、ウィリアム・ダルリンプルが著書『黄金の道:古代インドはいかにして世界を変えたか』で論じているように、このハードパワーによる単独の行為は異例であった。 1000年もの間、真の永続的なインド帝国は征服の帝国ではなく、文化の帝国でした。剣ではなく、哲学、宗教、芸術、言語の魅惑的な力で築かれた「ソフトパワー」の帝国でした。
支配的で文化的に拡張主義的なインドというこの物語に馴染みがないと感じるのは、ダルリンプルが示すように、この物語自体が長きにわたる歴史解釈の戦いの犠牲となってきたからだ。一世代にわたり、植民地時代のフランスの歴史家たちは、大インド協会のインド民族主義者たちの助力を得て、この古代の拡張を自らの「文明化の使命」を美化する鏡とみなし、古代インド植民地やヒンドゥー教徒のディアスポラという枠組みで捉えてきた。
しかし、脱植民地化の進展に伴い、東南アジアの新興独立諸国の学者たちは、古代インドの植民地主義という概念に当然ながら反発し、東南アジアの大学の学部では「インド化」という概念自体がほとんど忌み言葉となるほどでした。ダルリンプルの研究は、歴史記録を対位法的に読み解くという点で重要です。この手法によって、ダルリンプルは支配的でありながらも競合する二つの物語構築を解体しています。彼は植民地時代の歴史家たちの覇権主義的で東洋主義的な言説を批判すると同時に、植民地時代以前のインド国家の真の主体性と文化的力を独自の方法で消し去ってしまう可能性のある、純粋に反動的なポストコロニアル的枠組みに抵抗しています。競合するイデオロギーという知的瓦礫を一掃したダルリンプルは、この忘れられた帝国の仕組みを再構築します。
この伝承の主な媒体はサンスクリット語であり、聖なる言語から強力な文学・政治言語へと生まれ変わったサンスクリット語は、アジア全域で「人間の世界における神々の言語」となったと、ダルリンプルは述べている。これは粗雑な模倣ではなく、創造的な統合をもたらした。ダルリンプルはこれを「ピザ効果」に例えている。訪れたバラモンはクメール王のサンスクリット語の称号を認識したかもしれないが、目の前にいるのはカンボジアの顔立ちを刻まれた神々だったのだ。この活気に満ちたインド圏の知的中心地は、偉大なナーランダ大学であった。その名声は玄奘三蔵に6000マイルもの巡礼を強いたが、最終的にはトルコの狂信によって壊滅的な打撃を受け、ダルリンプルはこれを「文明の大惨事」と呼び、アレクサンドリア図書館の悪名高き焼失に匹敵する大惨事と評した。
ウィリアム・ダルリンプルは、考古学、碑文学、美術史、そして多くの忘れられた文書から得た約 200 ページのメモと参考文献という、驚くほど膨大な証拠を確かに集めました。
ダルリンプルの歴史書は、全体としては傑作であるにもかかわらず、インドの成功に対する偉大な反例である中国との、より闘争的な取り組みを切望させられた。近年、陸上を基盤とした「シルクロード」構想は、ピーター・フランコパンという最も雄弁な支持者を見つけた。フランコパン自身の功績は、中央アジアの商業と文化の幹線道路への注目を正しく再燃させた。ダルリンプルの『黄金の道』は、この説に真っ向から挑戦し、「シルクロード」という用語自体が19世紀にドイツの平凡な鉄道計画のために考案されたもので、今では北京のプロパガンダによって都合よく利用されていると主張して、この説を否定している。これは疑わしい主張である。マティアス・メルテンスが、この用語はフォン・リヒトホーフェンが考案したとされるよりも古いことを明らかにしているからだ。しかし、ダルリンプルは、ライバルである「シノスフィア」は「漢字表記の難しさ」によって妨げられた小規模な事業だったと指摘することで、この点を軽視している。これほど重みのある主張には、それ自身の徹底的な論争が必要である。つまり、ある文明が自国の文化の多くを輸出することに成功した一方で、その強力な隣国ができなかった理由について、より精緻な議論をしなければならない。
さらに憂慮すべきは、この偉大な作品がヒンドゥー極右によって武器化される危険性があることだ。世界を形作った輝かしいヒンドゥー仏教の過去を描いた物語は、いかに学術的で繊細なものであっても、その繊細さを削ぎ落とされ、台頭するヒンドゥー民族主義運動の材料として利用される危険をはらんでいる。
1998年、フロントライン誌でインドの核開発計画について書いたアルンダティ・ロイは、辛辣な言葉でこう述べた。「ええ、聞いたことがあります。爆弾はヴェーダにある、と。そうかもしれない。でも、よく探せば、ヴェーダにはコーラも見つかるでしょう。それがあらゆる宗教書の素晴らしいところです。何を探しているのかさえ分かっていれば、欲しいものは何でも見つかるのです。」そして、歴史も同じです。現代のヒンドゥー至上主義者は、自分が何を探しているのかを正確に理解しているため、過去に何があったかではなく、今そこに必要なもの、つまり一枚岩のヒンドゥー至上主義の黄金時代を見つけるのです。究極的かつ最も憂鬱な皮肉は、シンクレティズム、対話、そして国際的な交流の歴史を記録した本が、その正反対を唱える人々によって棍棒のように振り回される可能性があるということです。
ウィリアム・ダルリンプルは、考古学、碑文学、美術史、そして多くの忘れられた文献から集められた約200ページに及ぶ膨大な証拠を、確かに網羅している。しかしながら、本書を読み終えた今、私はある厄介なパラドックスと格闘せざるを得ない。
彼は、ヨーロッパ中心主義(そして今や中国中心主義)の過去の地図を修正しようと試みる中で、単に新たなインド中心主義の地図を作り出しただけではないだろうか。「インド圏」という概念そのもの、つまり受容的なアジアに光を放つ「サンスクリットの太陽」は、覇権的な重力を別のものに置き換えることに危険なほど近づいているように感じられる。その壮大な広がりは、クメール文化とジャワ文化の主体性と固有の才能を矮小化し、それらを輸入文化の単なる適応者として片付けてしまう危険性をはらんでいるのではないだろうか。
ナジュムス・サキブはダッカ大学で言語学を学んでいます。連絡先はXで@サキブ221ブです。
Bangladesh News/The Daily Star 20250911
https://www.thedailystar.net/books-literature/news/the-indosphere-and-its-discontents-3983041
関連