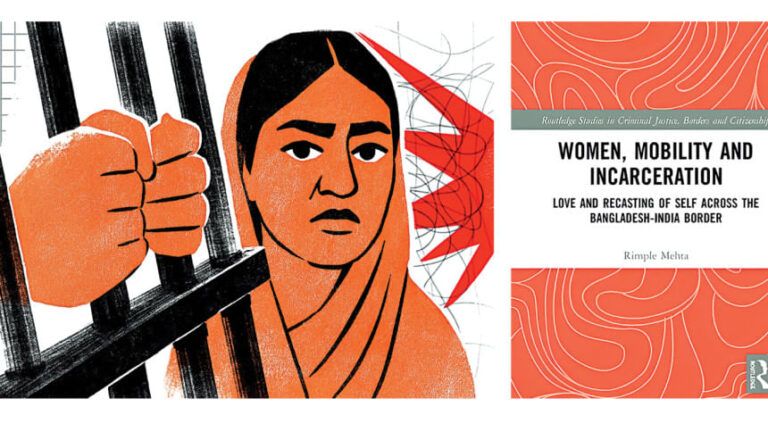[The Daily Star]2024年8月にバングラデシュで政治危機が勃発したというニュースを読んでいると、サルマさん、ハシナさん、ルンパさん(匿名性と守秘義務のため仮名を使用しています)をはじめ、2010年から2011年にかけてインドの刑務所で出会った数人のバングラデシュ人女性たちのことを思い出しました。彼女たちが語るバングラデシュの話や、彼女たちが声を揃えて「アマル・ショナール・バングラ」を歌う声がこだまする様子は、今でも私の心に鮮明に残っています。
彼らは今どこにいるのだろうか?危機は彼らにどのような影響を与えたのだろうか?シェイク・ハシナ首相の失脚とその後の政治史の変化は、インドとバングラデシュの国境、そして国境地帯に住む人々、あるいは国境を越えて移動する人々にとって何を意味するのだろうか?この混乱と変化の中で、国境を越える人々はそもそも考慮されるべきなのだろうか?それとも、彼らは依然として周縁に追いやられ、目に見えない存在であり続けるのだろうか?英国、米国、オーストラリア、インドといった世界各国の政治情勢の変化は、国境と移民の問題を政治的利益のために利用するか、あるいはこれらの問題に対して沈黙を守っている。これがバングラデシュでどのように反映されるかは、まだ分からない。
博士研究の一環としてコルカタの二つの刑務所で出会った若い女性たちは、有効な書類を持たずにインド・バングラデシュ国境を越えたため、1946年外国人法第14条(a)および(b)に基づき投獄されていました。暴力の軌跡、インドの刑事司法制度での経験、そして彼女たちの人生における名誉の役割についての好奇心から始まったこの研究は、国境の多様な概念、刑務所における愛の意味、そして彼女たちの人生におけるマーン・サンマーン(名誉)の役割を明らかにすることにつながったのです。
本書『女性、移動、そして投獄』は、私がインドのコルカタにある二つの刑務所で行った民族誌的フィールドワークに基づいており、そこでインタビューした40人のバングラデシュ人女性の経験を深く掘り下げています。彼女たちは18歳から22歳で、生計を立てたいという希望から、暴力や虐待のある結婚生活からの逃避まで、様々な理由でインドに来ました。国境の向こう側に住む親戚に会うために来た女性もいました。中には、インドとバングラデシュの国境を越えて人身売買された女性もいました。
女性たちの教育水準は、学校教育を全く受けていない人から平均5年間の正規教育を受けている人まで様々で、宗教を学ぶためにマドラサに通った人も少数いた。彼女たちの大多数は読み書きができず、貧しい家庭に育ち、農村部の仮設居住地で暮らしていた。幼少期から様々な労働に従事し、中にはインドに来る前に衣料品工場で働いていた女性もいた。既婚女性もいたが、1人を除いて夫と子供を連れてインドに来たのは彼女らだけだった。
刑務所でこれらの女性たちと過ごした時間は、研究だけでなく、研究者としての私自身にも大きな影響を与えました。彼女たちは、バングラデシュで、国境を越える過程で、そしてインドに到着してからも、暴力に直面しながらも、粘り強さと回復力の模範的な存在でした。しかし、暴力体験について質問すると、彼女たちはむしろ刑務所での愛の体験について語りたいと言いました。
刑務所における愛についての会話を通して、愛がいかに彼女たちの単調な日々の生活に意味を見出す力を与えているかが明らかになった。刑務所で愛について考え、愛の関係を築くことで、彼女たちは娘、妻、母親という役割に縛られない自己を探求することができた。彼女たちは愛の物語を通して、自らを表現したいと願っていた。これらの物語は、インド、バングラデシュ、あるいは国境で彼女たちが経験した構造的・制度的な暴力を反映していた。彼女たちは、私がフェミニスト研究と呼ぶものの視野を広げ、刑務所の女性に対する認識も広げてくれた。
女性たちの語りによって促進された二つ目の概念的探求は、国境の理解と、それを概念化する代替的な方法でした。女性たちの語りは、国境を批判するだけでなく、異なる視点から想像する可能性を示しました。刑務所に収監されていたバングラデシュの女性たちは、1971年の戦争においてインドがバングラデシュを支援したという両国の歴史的関係に基づいて、両国の関係を概念化しました。さらに、貿易、農業、その他の社会経済活動のために国境を越える日常的な移動は、女性たちにとって国境に対する流動的な理解を生み出しました。
彼女たちは、国境が人間によって構築されたものであることを強調することで、その自然さに疑問を投げかけた。都市、州、そして国という固有の性質を、彼女たちは想定していなかった。彼女たちはしばしば互いの理解を融合させ、インドとバングラデシュの間に連続性を生み出していた。彼女たちは、この国境の連続性と流動性(彼女たちの理解による)が、彼らを投獄へと導くことになるとは、知る由もなかった。
インドとバングラデシュという国民国家は、国境の概念をそれぞれ異なっており、それは彼ら自身の理解とは大きく異なっていました。そのため、女性たちは国境を越えるという行為について、ブール(過ち)とアポラード(犯罪)を区別するようになりました。彼女たちは、国境を越える行為がブールかアポラードかを決定する要因として、国境を越える際の意識と意図を挙げました。
マーン・サンマーンは、女性たちが物語の中で語った3つ目の重要な概念でした。マーン・サンマーンという概念は、女性たちの人生において重要な役割を果たしました。彼女たちはこの概念と格闘し、時にはジェンダー規範に従い、時には交渉したり抵抗したりしました。家の境界を越えて他国の国境を越えることは、彼女たちの不名誉につながると女性たちは信じていました。娘がインドの刑務所にいることで、より広いコミュニティの中で家族が恥をかくことを彼女たちは心配していました。
家族が彼女たちの投獄を知らない場合、女性たちは家族や地域社会の人々が彼女たちがインドでカラップ・カージ(性労働)に関わっていると推測し、人格に疑念を抱くことを懸念していた。刑務所内では、女性たちはバングラデシュの名誉を守ることに気を配っていた。インドで投獄されている間、母国の名誉を傷つけないよう、彼女たちはしばしば互いの行動を監視し合った。国境、警察署、刑務所、売春宿もまた、彼女たちが名誉の「喪失」を懸念する場所であった。バングラデシュに帰国した際に、家族や地域社会に受け入れられないのではないかと恐れていた。
抵抗というテーマは、様々な物語を貫いています。制度的・社会政治的規範への抵抗は、女性たちの物語において顕著です。彼女たちは被害者としてではなく、自らの存在条件を積極的に変革する主体として描かれることを望みました。彼女たちは、暴力やその他の社会経済的脆弱性から安全と安心を求めて、ある場所から別の場所へ、ある国から別の国へと移動しました。移動のたびに、彼女たちはさらに脆弱な立場に置かれ、監禁状態が生み出されました。例えば、バングラデシュでの家庭内暴力から逃れようとしたことで、インドへの人身売買に遭いました。売春宿からの逃走に成功したことで警察に捕まり、最終的にインドの刑務所に収監されました。自由を求める彼女たちは、何らかの形で監禁に直面しました。加害者や場所は変化しましたが、暴力と周縁化は彼女たちの生活の中で変わりませんでした。それでも、彼女たちは生き続けました。
彼女たちは国境という概念に挑戦し、愛の関係を築くことで刑務所の単調で性的な要素を欠いた空間に抵抗し、研究者としての私の方法論的アプローチにさえも挑戦しました。彼女たちは互いに連帯感を築き、刑務所当局から利益が脅かされるような状況でも支え合いました。こうした連帯感はしばしば脆く、刑務所内の限られた資源の中で緊張状態になることもありました。それが、競争的な主張の根拠となったのです。
私が出会ったバングラデシュ人女性たちの物語は、インドとバングラデシュの国境を越えてインドで投獄された際に彼女たちが経験した苦痛、恥辱、そして欲望について語ってくれました。彼女たちは、彼女たちを単にインドにおける「不法」移民として捉えるのではなく、彼女たちの生きた現実に人道的なアプローチをするよう私たちに強く訴えています。
こうした感情を他者と共に経験する中で、彼女たちは「自己」を再構築するプロセスを経た。刑務所内では、規範的なジェンダーロールから外れた自己像を描いていた。インドの刑務所という匿名性は、たとえ一時的であっても、彼女たちに自己を再構築する空間を与えた。こうした自己再構築のプロセスを経ていく中で、彼女たちは「外国人」「囚人」「女性」として直面する構造的な不利な状況を乗り越えていった。国境における制度化された暴力への恐怖は、刑務所を出た後の未来への想像を阻み続けた。送還の時期とプロセスを取り巻く不確実性も、背後に影を落としていた。
この本は、サルマ、ハシナ、ルンパのような女性たちが置かれている状況についての認識を高め、国境を越えて移動し、その結果投獄される人々の現実を人間的な視点から見ることを目的に執筆されました。
リンプル・メータ氏は、西シドニー大学社会科学部の社会福祉および地域福祉の上級講師です。
Bangladesh News/The Daily Star 20251011
https://www.thedailystar.net/slow-reads/big-picture/news/who-cares-about-bangladeshi-women-prisoners-india-4006966
関連