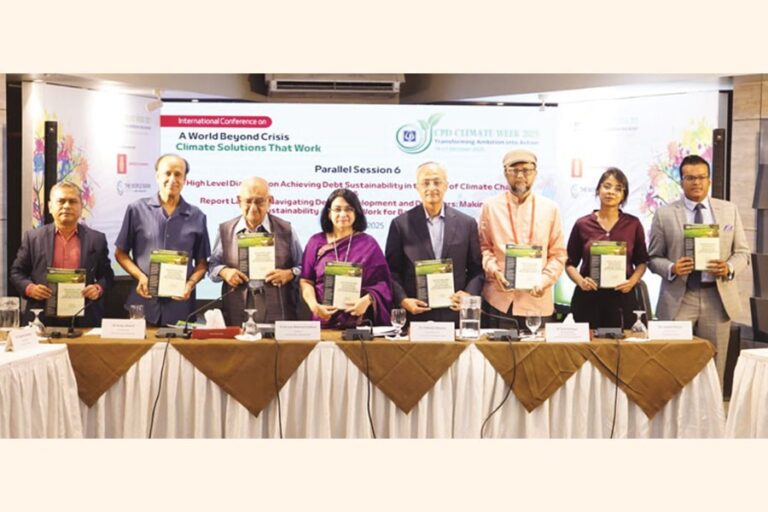[Financial Express]標準的な公的債務持続可能性分析には、対外債務の持続可能性と国内債務の持続可能性という2つの要素があります。これらは相互に関連していますが、多くの場合、異なる側面を持っています。どちらも非常に重要です。そのため、世界銀行と国際通貨基金(IMF)が実施する従来の債務持続可能性評価(DSA)は、総債務の持続可能性に正しく焦点を当てています。バングラデシュの状況では、国内債務の持続可能性は対外債務の持続可能性よりも大きな政策課題です。特に、財政安定性と流動性に関する懸念は、対外債務よりも国内債務とより密接に関連しています。
この点を最も簡単に説明する方法は、バングラデシュにおける債務持続可能性問題の推移を見ることである。総債務対GDP比は時間とともに低下しており、2002年度の国内総生産(GDP)の48%から2025年度には39%に低下している。これは、同期間に対外債務がGDPの34%からわずか15%に大幅に減少したためである。一方、国内債務はGDPの13%から23%に上昇している。この総公的債務の構成の変化を反映して、国内債務のコスト増大により金利コストはGDPの1.6%から2.2%に上昇しており、国内債務はGDPの1.3%から1.9%に上昇しているのに対し、対外債務の金利上昇にもかかわらず対外債務の金利コストはGDPの0.3%で横ばいとなっている。
審査対象論文のタイトル(債務、開発、災害を乗り越える:バングラデシュにおける債務持続可能性分析の有効性)が示唆するように、本論文では対外債務の持続可能性に焦点が当てられています。しかし、56~61ページでは、論文は総公的債務の持続可能性へと焦点を移し、財政の持続可能性の問題が持ち込まれています。対外債務の持続可能性と総債務の持続可能性を明確に区別することで、論文の質が向上すると考えます。総債務の持続可能性では、国内債務が主要な構成要素であり、財政の持続可能性と流動性制約の問題が重要かつ重要となります。
本稿では、流動性制約が対外債務の持続可能性にとって問題ではないことを明確にすることも有益である。これは、PPG対外債務の総債務返済コストを見れば容易に説明できる。2025年度の債務返済コストはわずか34億米ドルで、そのうち償却費は20億米ドルである。これは、総輸出収入810億米ドルのわずか4.2%に過ぎない。対外債務(EXT)構成の金利コストが増加していることは承知している。しかし、世界銀行とIMFDSAのシミュレーションが裏付けているように、現在の加重平均金利コストが1.4%から2.9%に倍増したとしても、対外債務に流動性制約は生じない。
さらに、過去15ヶ月間、外貨準備の積み増しと為替レートの安定化を目的とした特別BOPファイナンスにより、PPGの対外債務は急速に増加しました。そのため、債務返済を含むすべての対外債務指標は、2026年度と2027年度に弱まる見込みです。しかしながら、IMF・世界銀行のDSA(対外債務返済見通し)は、この一時的な変動は2028年度以降は安定すると示しています。返済リスクは最小限にとどまります。
EXT(輸出超過)の支払い問題を引き起こす可能性があるのは、民間および公的機関の無保証借入金を含む総EXTを考慮した上で、大規模な輸出ショックが発生した場合です。この事象の発生確率は低いですが、それでも支払い危機は民間部門の債務、特にST貿易信用に影響を与えるでしょう。PPG債務は支払い危機の影響を受けません。
2つ目の方法論的・分析的問題は、気候変動の影響をDSA分析にどのように組み込むかという点である。これにはいくつかの方法がある。一つは、是正措置が講じられない限り、気候変動のコストは物的資本と土地生産性の破壊によって平均GDP成長経路を低下させると主張することである。これは、ベースケースと比較して、気候変動による成長経路が低いケースを示す。DSAの感度分析は、債務対GDP比と輸出対GDP比を上昇させる。もう一つの方法は、気候変動の是正措置によって総公共支出が増加し、財政赤字と公的借入が増加すると仮定することであり、これは本稿で採用されている方法である。ただし、これは必ずしも本稿で想定されているように対外債務の1対1の増加につながるわけではないことに注意する必要がある。
実際、追加支出の多くは国内借入によって賄われる国内支出に転嫁されると主張する方が論理的です。自然災害に関連する救援・復興関連支出は、主に現地費用支出です。海外支出は主に輸入資本財であり、被害対策全体に占める割合は低くなります。したがって、このアプローチでは、国内債務への圧力が高まると想定する方がより合理的なモデル化方法となります。したがって、既に増加している国内債務負担を考慮すると、気候変動の最大の影響は、対外債務ではなく、国内債務の財政的持続可能性に及ぶことになります。
実際、それは現実です。私の知る限り、これまでの気候変動適応・緩和策の費用は必要額をはるかに下回るだけでなく、そのほとんどが国内資源から賄われています。世界的な現実を踏まえると、世界気候基金(GCF)やその他の気候基金からの資金提供を期待して気候変動対応戦略を策定することは、必ず失敗するでしょう。気候変動に起因するコストの多くは先進国からの炭素排出に起因するという正当な主張を今後も主張し続けることはできますが、実際には、多額の世界的な資金支援が得られる見込みはほとんどありません。
例えば、緑の気候基金(GCF)は2010年に設立され、2020年までに毎年1,000億米ドルを動員するという誓約を掲げました。実際の成果はどうだったでしょうか?2018年時点で、地球規模気候基金(GCF)設立後8年間で合計93億米ドルが集まりました。第1次増資では、2020~2025年にかけてさらに100億米ドルが拠出されました。第2次増資では、2026~2030年にかけてさらに106億米ドルが拠出されました。すべての誓約が履行されると仮定すると、GCFの資金総額は20年間で299億米ドルに達する見込みです。これは年間15億米ドルに相当し、2020年までに年間1,000億米ドルという目標達成には程遠いものです。また、重要なのは、バングラデシュに対するGCFの資金総額は、過去15年間でわずか4億6,100万米ドルにとどまっていることです。これは年間3,000万米ドルというわずかな額に相当します。
したがって、気候変動による被害への対応のための世界的な資金調達の拡大に向けて引き続き取り組むべきである一方で、政策レベルでは国内資源の動員に重点を置く必要があります。私はこの分野で研究を行ってきましたが、炭素燃料の適切な価格設定、炭素税の導入、汚染者負担原則、受益者負担原則の導入などを通じて、気候変動対策のために国内資源を動員する余地は大きくあります。
本稿では、世界的な気候変動対策資金の現状を認識し、環境財政改革を通じた国内資金調達の必要性をより強調する必要がある。これはバングラデシュの政策立案において大きく欠如している要素である。さらに、公共支出全体、特に公共投資プログラムを気候変動対策に配慮したものにするための十分な余地があり、これにより、対外債務負担を必ずしも増加させることなく、気候変動対策資金への支援を強化するために、MLT対外借入総額を再調整することが可能になる。気候変動対策を予算編成とPIP(公共投資計画)に主流化することは、本稿で強調すべき最重要政策課題である。
サディク・アハメド博士は、バングラデシュ政策研究所(PRI)の副会長です。sadiqahmed1952@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20251024
https://today.thefinancialexpress.com.bd/views-reviews/external-debt-sustainability-in-the-face-of-climate-change-1761230376/?date=24-10-2025
関連