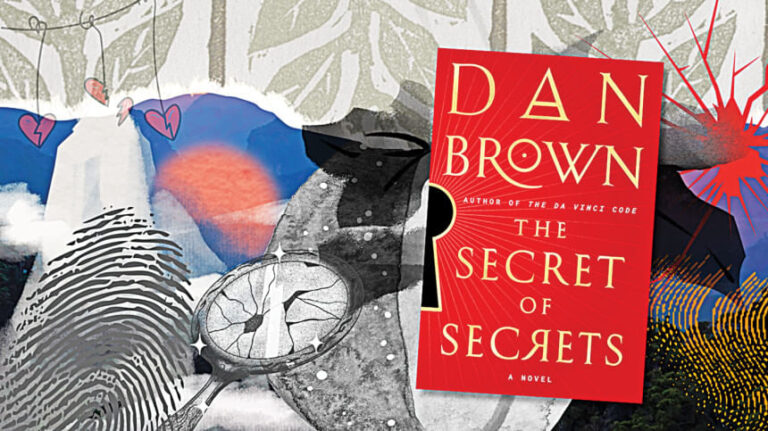[The Daily Star]2025年、ダン・ブラウンがついにロバート・ラングドンの6作目の冒険小説『秘密の秘密』で戻ってきたとき、『ダ・ヴィンチ・コード』(ダブルデイ、2003年)を夢中で読んだ世界は、その物語に対して複雑な反応を示した。
ここで、ロバート・ラングドンはキャサリン・ソロモンの画期的なノエティック科学の論文をめぐる陰謀に巻き込まれる。その研究は、人間の意識は脳とは独立して存在することを示唆している。ソロモンの論文が危険な知識の境界を越えると、強大な勢力がそれを破壊しようと動き出す。サーバーは消去され、論文は消失し、ラングドンは暗殺者とチェコの諜報機関に追われながらプラハを駆け巡る。
表面的には、これはブラウンの典型的な手法のように見える。短い章にクリフハンガーが散りばめられ、サスペンスを演出するために戦略的に情報が隠され、プラハのユダヤ伝承に由来する神話上の悪役ゴーレムが、人間の制御能力を超えた危険な知識のメタファーとして再解釈されている。しかし、ブラウンのアプローチには根本的な変化があった。最も顕著な変化は、宗教的象徴から意識研究への転換である。ブラウンは明らかに、この転換が単なる置き換えではなく進化を象徴するものであることを意図している。しかし、科学的内容は、かつてブラウンの歴史パズルが持っていた重みや一貫性を決して達成していない。
以前、ブラウンが「最後の晩餐」やベルニーニの彫刻に陰謀を織り込んだ際、視覚的なシンボルそのものが読者が理論的に考察し解読できるパズルのピースとなった。芸術は現実であり、歴史は現実であり、ブラウンの解釈は具体的な何かに根ざしているように感じられた。しかし、意識は本質的にこのような扱いには抵抗する。ブラウンは超心理学の実験を参照し、量子力学を持ち出し、それらをキャサリンの研究を通して結びつけることで、あたかもそれらが一つの啓示へと自然に繋がっているかのように見せることで、明白な視界の中に隠された真実という感覚を醸し出そうとしている。しかし、その繋がりは構造的というよりは表面的で装飾的なものにとどまっている。本書は深遠な問いを繰り返し示唆するものの、真の深みや厳密さをもってそれらを探求することはほとんどない。本書を読んでいると、意識操作やノエティック実験に関する膨大な説明を何ページにもわたって読み進めた末に、過剰な情報を流し読みしているような感覚に陥った。情報は登場人物を照らし出したりプロットを進めたりするというよりも、むしろ空間を埋め尽くし、実質的な洞察を与えずに、中身があるかのような錯覚を生み出している。
ブラウンの独自の手法が成功したのは、抑圧された知識や隠された歴史に対する特有の文化的不安を巧みに捉えたからである。何世紀にもわたって宗教芸術の中に天地を揺るがす真実が隠されてきたという考えは、陰謀論の文化に染まりながらも、より知的に尊重されるべきものを求める読者の心に響いた。小説の冒頭に置かれた悪名高い「事実」のページは、フィクションと現実を意図的に曖昧にし、読者に単なるスリラー小説ではなく、真の秘密に触れているような感覚を与えた。
しかし2025年になると、読者は陰謀論と誤情報の渦に溺れてしまう。ブラウンが決してその手法を捨てないことは、今や誰もが知っている。秘密結社、暗殺された重要人物、象徴を解読しながらランドマークを駆け抜けるという手法だ。問題は、彼がそれらを義務ではなく必然と感じさせることができるかどうかだ。
そしてここで、この小説は核心的な矛盾を露呈する。ブラウンは定型を維持しつつも、同時にそれを超えて進化できることを証明しようとしている。長年のファンには懐かしい記憶を呼び覚まし、同時により現代的な感覚を期待する新しい読者も惹きつけたいのだ。意識と最先端の神経科学について書きながらも、初期の作品を特徴づける古代ミステリーと現代スリラーの融合という構造は維持したいのだ。そして何よりも重要なのは、ロバート・ラングドンを、ドジな学者でありながら、同時にジェームズ・ボンドであり続けさせたいと考えている点だ。
この最後の点は問題の核心を突いている。オリジナルのラングドンは、閉所恐怖症の教授で、肉体ではなく知識で謎を解き、慎み深さと学究的な非現実的な態度が暴力の中でコミカルな安らぎを生み出し、危険をよそに切り抜けながらも、素晴らしい知的飛躍を遂げていた。しかし、このラングドンは恋愛関係にあり、同年代の男性とは思えないほどの肉体的な偉業を成し遂げ、まるでボンドのような器用さで跳躍し、戦う。
プラハは平坦化に苦しんでいる。700もの尖塔、ゴシック建築、そして何世紀にもわたる石畳の道の重みといった、ブラウンの美学にふさわしい街であるはずなのに、情報は断片的に伝わってきて、雰囲気というよりは教育的な印象を与える。『天使のローマ』 悪役の構成は、ブラウンが自身の手法を進化させる難しさを如実に物語っている。プラハのユダヤ神秘主義に由来する怪物であるゴーレムは、知識が制御を超えてしまう危険性を象徴し、神話的あるいは宗教的な原型を体現した初期のブラウン作品の敵役を彷彿とさせるため、完璧に機能するはずだった。しかし、『秘密の秘密』のメインの敵役には、この脅威と複雑さが欠けている。フィンチ氏とブリジタ・ゲスナー博士は、漫画的な誇大妄想ではなく、国家安全保障と科学の進歩に対する真の信念に突き動かされているように描かれている。しかし、この理性的さこそが、かつてブラウン作品の悪役が持っていた神話的な力を彼らから奪っているのだ。彼らはあまりにも現実的で、説明がつきやすく、初期の敵役を印象深いものにしていた劇的な狂気の要素が欠けている。
プロットにも同様の矛盾が見られる。ラングドンとキャサリンはTEDトーカーとなり、主に情報を伝える存在となる。各章は会話というより脚本のような台詞で始まる。これはブラウンの作品において常にある程度当てはまることだが、本作ではその仕組みがより明白になっている。キャサリンの原稿は、誰もが追い求める究極の賞品として機能しているが、その構造的な必然性以外には、その重要性は決して感じられない。
ブラウンは意識研究の緊急性を喚起しようと試み、キャサリンの発見が人間の理解に革命をもたらす可能性、あるいは架空の施設「スレッショルド」のようなプロジェクトを通じて諜報機関に武器として利用される可能性を示唆している。しかし、以前の作品で宗教的な秘密が扱われたように、その危険性は具体的なものではない。イエスがマグダラのマリアとの間に子供をもうけた可能性は、キリスト教の根本教義を脅かすものだった。意識が脳の外に存在するという示唆は興味深いが、以前の作品ほどの文化的潮流には欠けている。制度的な権力に挑戦したり、文明の基盤を揺るがしたりするものではない。
おそらく根本的な問題は、ブラウンが自ら窮地に陥っていることだろう。彼はあまりにも成功し、あまりにも独特な手法を生み出したため、少しでも逸脱すればコアな読者層を遠ざけてしまう恐れがある。しかし、毎回斬新さを失わせながら同じ構成を繰り返し続けることは、批評家から拒絶され、読者の疲労を招くことは間違いない。
カジ・ライダ・アフィア・ヌサイバ さんの寄稿者です。
Bangladesh News/The Daily Star 20251030
https://www.thedailystar.net/books-literature/news/sacred-art-consciousness-leap-too-far-4022511
関連